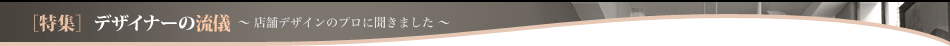問い
last update:2025-03-27 15:52:25.0
店舗併用住宅の建築を予定しています。申請を含め、設計の際にはどのような点に注意が必要ですか?
店舗併用住宅を出店する場合、通常の店舗に比べて申請などをプラスで行う必要があります。
出店をスムーズに行うために、どのようなポイントに注意すべきか店舗デザイナーに回答していただきました。
- 新着順
- 投稿日順
-
入山 裕貴 2025-03-27 15:52:25.0投稿
流儀
A. 店舗併用住宅は、「住宅」と「店舗」両方の機能を持つ建築物のため、設計・申請において以下の点に注意が必要です:
1. 用途地域・建築基準法の確認
地域の用途地域(例:第一種住居地域、商業地域など)によって、店舗の種類や規模に制限がある場合があります。
建ぺい率・容積率、斜線制限、防火地域の条件なども要確認です。
2. 店舗と住宅の動線の分離
プライバシー確保や安全性の観点から、住宅部分と店舗部分の出入口や動線は分ける設計が理想的です。
共用玄関とする場合も、適切な間仕切りやアクセス制御が求められることがあります。
3. 消防・防火対策
店舗部分に不特定多数の人が出入りする場合、防火区画や避難経路の確保、防災設備(非常ベルや誘導灯など)の設置が必要になります。
住宅と店舗の境界に耐火性能のある壁や扉が必要となる場合もあります。
4. 騒音・匂いへの配慮
飲食店舗の場合、住宅部分への騒音・匂いの影響を防ぐ設計(排気ダクトの位置・遮音構造など)が求められます。
5. 設備の独立性
電気・水道・ガスなどのインフラについて、店舗と住宅でメーターを分けると、管理や請求が明確になります。
給排水設備の位置も慎重に検討が必要です。
6. 確認申請に関する注意
店舗の用途や面積によっては、「特殊建築物」に該当し、建築確認申請の内容が複雑になる場合があります。
用途変更や既存建物のリノベーションの場合は、事前協議や事前審査が必要なケースもあります。
7. 内装制限と仕様の違い
店舗部分は不特定多数が利用する空間となるため、使用できる内装材に不燃材料や準不燃材料などの制限がかかることがあります。
もし具体的な計画地や業種(例:カフェ、美容室、物販など)があれば、それに応じた詳細なアドバイスも可能です。お気軽にご相談ください。 -
匿名さん 2021-10-08 10:22:07.0投稿
流儀
まず、建築予定の場所にご希望される店舗の種類が建築可能かどうかを検討することが重要です。
建築基準法で決められている地域によっては、ご希望の店舗が建築できない場合がありますので注意が必要です。
設計としては、住宅部分のプライバシーが店舗営業時も確保されるように配慮してあげることが必要かと思います。
飲食であれば店舗からの匂いや音の問題、美容系なら住宅部分からの匂いや音のケア、そして住宅に住む人と店舗のお客様の動線が重ならないようそれぞれどこにエントランスを配置するかは設計段階で重要なポイントになってくるかと思います。
-
流儀
どんな業種をされるかで少し内容が変わってきますが、御来店して頂くお客様側から考えますと、お店の滞在中に生活音などがするとちょっとがっかりするかもしれませんね。そのあたりの防音対策を検討されると良いと思います。申請関係については、建築確認申請などがあると思いますが、ある程度建築士さんの方で申請されますので、建築士さんからご説明頂く必要事項の記入などに対応していけば難しくないと思います。保健所が関係する業種ですとこちらも申請書類がありますので事前(工事前)に相談にいかれることをおすすめします。 こちらも店舗に詳しい方(内装業者)などに指示をいただく事もできると思います。
ご参考になれば幸いです。 -
匿名さん 2020-12-14 12:28:52.0投稿
流儀
構造によっては異種用途の区画が必要になります。また、厨房は火気使用室にあたる為、不燃材による区画が必要となります。この辺りは規模や構造によって違いがある為、建築士の方によく話しを聞いた方が良いと思います。建築士の方は建築の設計や建築基準法には精通していますが、店舗のデザインに精通していない事も有ります。店舗のデザインは設計とは異なる感覚が必要なジャンルの為、建築設計も店舗デザインも得意な会社様に頼むのが良いと思います。

-
匿名さん 2020-12-11 09:47:59.0投稿
流儀
店舗業種を仮に飲食業として簡単に回答致します。
消防署、保健所が十分に納得できる建築が望ましく、特に衛生面より生活雑菌を厨房に持ち込まないレイアウトが肝要です。
住宅側より申せば、夏などに天アイ厨房の熱が伝わりにくい構造が望ましいです。
-
匿名さん 2020-10-26 09:40:03.0投稿
流儀
こんにちは。 敷地にはその地域によって、行政で決められた「用途地域」と言うものがございます。その用途地域によって店舗併用住宅の「店舗部分」の最大面積が決まっている地域もありますので、まずは敷地を選定される場合には設計士や不動産の方にお聞きされる方が後からの間違いが無くなります。
また、どのような店舗かにもよりますが、物販の場合は水回り(トイレや手洗い)を2つ作るかどうかや、居住スペースと店舗スペースの行き来の動線に気を付けてください。
ご参考になれば。
-
流儀
店舗併用住宅の場合は、建築基準法により、立てることができる土地かどうか、その用途は何かなど、様々な決まりがあります。
細かい内容が多いので、一級建築士にご相談されることをお勧めします。 -
匿名さん 2018-02-26 12:21:15.0投稿
流儀
店舗併用住宅の場合、法律による規制があることがあります。
用途地域によって面積、住宅と店舗の面積の割合、開業出来る業種が異なるため事前に確認が必要です。
デザイン面では、店舗と住宅の関係性をクライアントの暮らしに寄添ったゾーニングにすることが大切です。
-
流儀
設計の前に、基本的に店舗部分は、住宅ローンが適用されません。
店舗併用住宅の建設資金として、住宅ローンを金融機関へ申し込む際は、住居部分は住宅ローンとして申し込み、店舗部分は事業資金として融資の申請を行います。
金融機関によっては、個々の資産状況や取引実績、業歴や所得などを見て、店舗面積が半分以下であれば住宅ローンとまとめて申し込むことが出来たり、住宅ローンと事業資金用ローンの両方を用意してくれたりするところもあるようです。
勿論、手持ちのお金で店舗部分の資金を用意できれば、通常の住宅と同じことで、住居部分の建設用に住宅ローンだけ申し込めば、店舗部分の広さは関係なく審査を受けられます。
ただし、長期の住宅ローンである「フラット35」を申し込む場合は、住居部分が全体の半分以上を占めていることも条件にされています。低金利・長期の住宅ローンで費用負担を抑えながら店舗併用住宅を建てたい場合は、店舗部分を全体の半分以下に抑えるなど、設計の段階から対策を取ることが必要です。
ただし、これらの条件を整えていても、そもそも法律で店舗の建築が制限されていたりすることもあります。 -
匿名さん (デザイン) 2018-02-20 08:59:48.0投稿
流儀
店舗併用住宅の場合
まず用途地域と開店できる店舗の規模をリサーチすることが大切です
次にプライバシーと店舗の区分け
また動線や出入り口のデザインがとても大切です
近隣が住宅の場合はあらかじめ近隣への配慮したデザインも必要ですが
何よりバランスのよい職住接近のレイアウトと設計をクリアしましょう
住宅デザインと店舗デザイン両方の視点から的確なデザインを実現する必要があります
-
匿名さん 2018-02-19 09:03:37.0投稿
流儀
以前デザインした店舗併用住宅の場合、第一種低層住居専用地域だったため、店舗部分の床面積が50m²以下で、住居部分の半分以下という規制がありました。現在お住まいの建物を店舗併用住宅にする場合も、新たに場所を探す場合も用途地域とそこで営業できるお店の業態を調べておく必要があります。

-
流儀
法的条件や立地を調査し店鋪部分の面積比率、住宅部との出入口の分離、導線が交差しない様に注意が必要です。又、外観は店鋪優先のイメージにする事や電気や空調、給排水設備などの検討が大切です。
自分に合ったデザイン会社が見つかる!
お店のイメージを登録するだけで、平均7社から提案が受けられます。