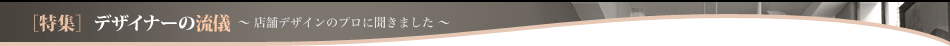問い
last update:2022-04-04 10:57:43.0
デザインの著作権を守る為にしている対策はありますか?また権利保護の観点で施主側に守ってほしいことがあれば教えて下さい。
デザインと著作権・意匠権に関わる内容です。
最近、ニュースで話題になっているテーマですが、店舗デザインの業界でも、
悪意のあるなしに関わらず、疑惑を含めて少なからず生じている問題です。
店舗デザイナーの方が普段実行している対策などについてお聞きしてみました。
- 新着順
- 投稿日順
-
寺島 彰吾 2022-04-04 10:57:43.0投稿
流儀
私たちはすでに多くのデザインや表現が生み出された後の社会に生きています。また、技術の発達のより過去に生み出されたデザインなどの表現が容易に検索できるようになり、可視化されるようになっています。
私としては最終的に引き渡しをしたらデザインすべてお客様に譲渡している認識ですので守ってほしい事は特にございませんがデザインを変更したり少しいじりたいなどはデザイン原点を作ったデザイナーと考えていただきたいのは正直な要望です。世界観のブレないデザインで店舗展開をおすすめいたします。
-
匿名さん 2022-02-14 16:11:54.0投稿
流儀
店舗のロゴマークやネーミングについては著作権を守る方法は色々あるのですが、店舗デザインについては難しいのが現状です。
僕も何度か真似をされて、酷似した店舗を見たことがあり、とても残念な気持ちになります。
ただ、コピーされても所詮コピーはコピーで、オリジナルを超えることはありません。
-
匿名さん (デザイン) 2022-01-17 09:40:53.0投稿
流儀
日本において空間デザインに対する
知的財産や著作権に関しての認識は残念ながらまだ非常に低いのが現状です
JG1920ではあくまでシンプルに取引契約において契約金から始まり
最終金の受理と同時に著作権が施主側に移行するスタンスでおります
映画であれ音楽であれ著作権利は最も重要な権利保護の一つですが微力ながら
空間におけるデザインの権利と価値を施主の認識とともに高めていけるよう尽力しています
また最近の事例から本質的な空間の価値とはデザイナーと施主双方で
高め合うものだと確信しております
-
匿名さん 2021-12-22 09:36:26.0投稿
流儀
特許を出していない限り著作権の主張は難しいと考えています。またデザインそのものを知的財産権として特定するのも難しいのかなと。ただ設計者としては世界に一つしかないデザインと考えてお客様にご提案していますので、2者が相互に理解しあえていたら良いのかなと思います。

-
匿名さん 2021-12-22 09:36:15.0投稿
流儀
出来ればお施主様には図面の取り扱いにはご注意願えればと思います。図面に著作権があるのかどうか難しいところですが、お施主様と設計側の大切な意思疎通の道具ですのでお互い取り扱いには注意したいものです。失礼いたしました。

-
匿名さん 2021-12-14 10:27:33.0投稿
流儀
こんにちわ。なかなか難しい問題ですね。正直なところ我々はあまり考えないようにしています。デザインで世の中が楽しくなるのであれば、いいアイデアはみんなで共有できればよいのかなと思っています。もちろん悪用や道義的な問題が発生すれば別ですね。
お施主様には計画段階などの図面やアイデアを同業者(設計)に見せて競わせるような形にさせるのは控えていただければ幸いです。
参考になれば。
-
匿名さん 2021-05-21 11:32:16.0投稿
流儀
建築に限らず、アートやデザインに関する権利の主張は難しいのが現状です。「芸術作品」には著作権が認められていますが、「創作」そのものには認められていません。権利の確立ではなく、モラルやマナーのといったシステムの創設ということで「クリエイティブコモンズライセンス」等がありますが、基本的には自発的に発信する仕組みです。
一方で、権利の主張を目的としていないデザイナーも数多く存在しています。私もそのひとりです。そもそも、私は自分のデザインを「作品」と捉えたことは殆ど無く、あくまでも「仕事」と捉えています。店舗デザインであれば尚更です。店舗デザインの目的は、そこでクライアントが商売をし、売上げと利益を上げることです。私のデザインを評価してもらうことが目的ではありません。どんなに私のデザインが評価されようとも、そこで営まれる商売が繁盛して永く愛されないことには意味がないのです。
クライアントの事業がきちんと成立し、その社会貢献に一役買うことが出来れば、私はアノニマスな存在で構わないと考えています。
-
匿名さん (デザイン・グラフィック・監理) 2021-04-20 09:41:33.0投稿
流儀
日本の法律ではデザインを守る限界がありますし、社会風土からしても権利を守ることに困難が多いのは事実です。
そうした意味でも施主様にはデザインコンペなどと称しデザインを出させ、見積の安いほうにそのデザインを実行させるなどのモラルのないことは控えていただきたいです。
弊社ではデザインをで移出する際は必ずそのデザインを「お買い上げいただく」意味で契約をし、契約金をいただいております。
その場合、安く施工できる会社に依頼するのはお客様の自由だと思います。
-
匿名さん 2020-12-18 09:53:56.0投稿
流儀
正直店舗内装業界では完成した店舗に於けるデザイナーの立場での意匠権など知的所有権を守る行為は殆どなされておりません。
我々の業界では真似されてこそ価値が上がると捉える事が多いのではないでしょうか。
ブランド様など施工主様ではブランドカラー等厳密な既定の元、国際パテントを取得されている事が多く、弊社からも制作・施工に携わる協力業者へは、他案件での同等利用をさせない為の契約書を結び、お店様の望まぬ情報が漏洩せぬ為の対策は個々のHP、SNS等も含め監視する体制を設けております。
弊社も然りですがスーパーブランド様、ラグジュアリーホテル様に於いては、価格帯並びに同等仕様のコピーを避ける為、施工業者の実績開示を望まれず、厳格な契約の上、情報漏洩せぬ様取り決めている事が多い様に捉えております。
施工前ではデザイナーが提案致しますデザインの全てがラフ画も含めてデザイナー個人又はデザイン会社が有する作品であり、知的所有権はデザイナー個人又はデザイン会社が有する事となりますので、デザイナー意思が反映されぬ形での無断利用(他の施工業者やデザイナー)に開示され類似する店舗を施工された場合は法的処置に踏み切る事も御座いますので、信頼関係を以って御対応頂けるよう望むばかりです。
-
匿名さん 2020-05-28 09:44:44.0投稿
流儀
弊社では図面類に全て設計図書及びデザインパースなどの取り扱いに関しての注意書きを入れております。大半のお客様にはご理解いただけている事ではありますが、心無い一部のお客様には転用されたり断りなく開示されてしまうのは正直防ぎようがありません。
お願い事項としてになりますが、お客様には設計図書は商品でありご購入(ご契約)頂いてからはじめてお客様の所有物になる事をご理解頂きたいものです。取り扱われている商品を無断使用されたり、無銭飲食された事を考えて頂きたいものです…
-
匿名さん 2020-01-28 12:01:37.0投稿
流儀
弊社では、設計契約書に著作権に関する項目を設け、契約を結ぶ際にクライアントに詳細内容のご説明をしております。

-
流儀
店舗デザインは、真似をされてもイメージとして、お客さんからイタリアの街だとか言われます。
機能や形を特許庁に相談しても特殊な物以外はぼぼダメですね。
最低でもお店の名前やマークは商標登録しないと営業できなくなります。 -
匿名さん 2017-06-27 21:01:34.0投稿
流儀
図面の転用やパースの転用には注意していただきたいです。

-
匿名さん 2017-04-20 17:02:48.0投稿
流儀
インテリアデザインに著作権などナンセンスです。そもそも無法地帯。オリジナルは残り、モノ真似は淘汰されます。良いモノを作りましょう!!商道徳やデザインを軽視する事業主に真の成功はないはずです。

-
匿名さん 2016-06-21 13:31:29.0投稿
流儀
デザインなどのつくることに関する著作権については、社会として権利保護の方向性を間違っていると考えているので、私見を書かせていただきます。
つくることの本質的な喜びは、何かをつくるプロセスの中にあると思っています。
できあがった何かは、できあがった瞬間に自分の手を離れて、自然の中へ投げ出され、時間とともに壊れていく。風化していく。
そして、それが誰かの目に止まり、次につくられるものの参考となって、その背中を押す。今度はその人の喜びに変わる。
それが永遠に繰り返されるのが、つくることの理想で、そのようにして文化は高められてきたのだと思っています。
著作権を保護する、という考え方には、その理想に反するところがあるのは明らかで、今回のオリンピックのロゴ問題のように、一見似ているものをすべて排除する方向へ向かってしまう、という危険性があります。実際、応募する人にも選ぶ人にも自由が失われてしまった、という状況を目の当たりにしたのではないでしょうか。
一見似ている二つのものの微細な違いこそが創造力が結実したものである場合もあります。コピーなのか、コピーじゃないか、は少なくとも単純に外から判断できる類のものではありません。
また、単にコピーをすることは、そもそもそこにつくる喜びがないのだから、すでに罰を受けているようなものです。
一方で、現在仕事として進めているデザインに対する対価を著作権の保護によって主張するのはわかります。業界として、相見積とともに、複数のデザイン事務所が無料でデザインを提出するのを普通のことにしてしまったことがそもそもの問題です。
採用されなかったデザインは、ゴミのように社会から消されてしまいます。
私たちがアメリカにいたのは10年以上前のことになりますが、アメリカでは、インタビューのみを無料で行い、デザインはすべて有料で行われていました。
日本のデザイナーは一般にプライドが低い、と言えるでしょう。同時に、デザイン自体に対するプライドも低いと言われても仕方ありません。この点に関しては、早く日本もアメリカのように移行すべきだと思います。
弊社では、必ずクライアントと1対1でお会いして、双方の方向性が一致したことを確認してからのみ、デザインの提案をさせていただいています。どのような人であるか、をお互いに確認することが、著作権を守る、ということをことさら話題にしなくとも、結果として正当な対価をいただく結果につながっている、と思います。
しかし、正当な対価を受け取った後で、著作権の保護を主張するのは、もう他人の創造の障害でしかありません。それは、既得権益へとつながり、ただでさえ停滞しがちな社会を、もっと停滞させる原因のひとつになってしまうのではないでしょうか。
-
流儀
デザイン・設計契約を結ばさせていただく際に、契約書の中にデザイン著作権の条項を設け、両者承認のもと契約させていただいています。
また、トラブルとして多いのは、契約前に提案したデザインやプランを(一部等でも)拝借〜工事を行い、設計側には無報酬というパターンや、二店舗目以降を同じコンセプトでデザインする場合、オリジナルのデザイナーに無許可で複製してしまう、などだと思います。
その辺りも、設計契約やプラン開始時に、きちんとお話をさせていただく事が必要かと思っています。
自分に合ったデザイン会社が見つかる!
お店のイメージを登録するだけで、平均7社から提案が受けられます。