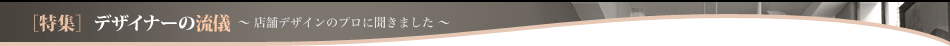問い
last update:2025-04-22 13:57:48.0
検討中物件がB1F等の地下階の場合、設計や施工をする上で注意をしなければいけないポイントはありますか?
地下階での出店をする場合は、ファサード部分の制限や設備などをプラスで確認する必要があります。
出店計画をする上での、注意する点や確認すべき点などをデザインの観点からもご回答して頂きました。
- 新着順
- 投稿日順
-
入山 裕貴 2025-04-22 13:57:48.0投稿
流儀
地下階(B1Fなど)の設計・施工においては、地上階とは異なる特有の課題が存在します。以下に、特に注意すべきポイントをまとめました。
⸻
1. 防水・防湿対策
地下階は地盤や地下水に接しているため、漏水や湿気のリスクが高まります。そのため、以下の対策が重要です。 
• 防水層の設計と施工:外壁や床下に適切な防水層を設け、地下水の侵入を防ぎます。
• 排水計画の策定:排水ポンプや排水路を設置し、万が一の浸水時にも迅速に排水できるようにします。
• 防湿材の使用:室内の湿度をコントロールするため、防湿材の導入を検討します。 
これらの対策により、地下階の快適性と耐久性を確保できます。
⸻
2. 換気と空調の確保
地下階は自然換気が難しく、空気の滞留や湿度の上昇が懸念されます。そのため、以下の点に注意が必要です。
• 機械換気設備の設置:強制換気システムを導入し、空気の循環を促進します。
• 空調設備の導入:温度と湿度を適切に管理するため、空調設備を設置します。
• 定期的なメンテナンス:換気・空調設備の性能を維持するため、定期的な点検と清掃を行います。
これにより、地下階でも快適な居住環境を維持できます。
⸻
3. 地盤調査と構造設計
地下階の建設には、地盤の状態や周辺環境を十分に把握することが不可欠です。以下の点を考慮しましょう。 
• 地盤調査の実施:地盤の強度や地下水位を確認し、適切な基礎設計を行います。
• 地盤改良の検討:必要に応じて、地盤改良工事を実施し、建物の安定性を確保します。
• 周辺建物への影響評価:掘削や工事による周辺建物への影響を評価し、必要な対策を講じます。
これらの対策により、安全で安定した地下階の建設が可能となります。
⸻
4. 法規制と許認可手続き
地下階の建設には、建築基準法や都市計画法などの法規制が適用されます。以下の点に留意しましょう。 
• 用途制限の確認:地下階での用途(居住、店舗、倉庫など)が法的に許可されているか確認します。
• 建築確認申請の提出:設計図書を作成し、所管行政庁に建築確認申請を行います。
• 消防法令の遵守:避難経路や防火設備の設置など、消防法令に適合する設計を行います。
これらの手続きを適切に行うことで、法的な問題を回避し、円滑な建設が可能となります。
⸻
5. 照明と採光の工夫
地下階は自然光が入りにくいため、照明計画が重要です。以下の点を考慮しましょう。
• 人工照明の計画:用途に応じた照度を確保するため、適切な照明器具を配置します。
• 光井戸やドライエリアの設置:可能であれば、光井戸やドライエリアを設け、自然光を取り入れます。
• 反射材の活用:内装に明るい色や反射材を使用し、光の拡散を促進します。
これにより、地下階でも明るく快適な空間を実現できます。
⸻
地下階の設計・施工は、専門的な知識と経験が求められます。信頼できる建築士や施工業者と連携し、計画を進めることが成功の鍵となります。 -
匿名さん 2023-12-20 10:02:30.0投稿
流儀
地階の物件で計画を行う場合、いくつかの注意点があります。
地階であるということは周囲が土に囲まれている状況が伺えます。建築基準法では居室の用途や面積に応じて最低限必要な窓などの開口部を設けることとされていますが、開口部を設けることができない場合には無窓居室となる可能性があります。無窓居室にあたると、内装制限、非常照明、換気設備、排煙設備など様々な点に注意が必要です。
他にも地上の物件にはない制約がある可能性がありますので事前の確認は必須となります。
また、デザインの面では店舗のファサードが地階になってしまうので道ゆく人の目に留まりにくかったりもします。目立たせて多くのお客を呼び込みたいのであれば地上に出す看板デザインや入口に存在感を待たせることが重要です。逆に外からは店内の様子が見えないため、看板や入口のデザインをシックなデザインにすることで隠れ家的な店舗計画もできるかもしれません。
法規の面では様々な注意点がありますが、それらをクリアできれば地下ならではの面白い計画ができそうですね。
-
流儀
物件がB1F等地下フロアの場合のポイントですが、これは上層階との共通事項ですが 搬出入の際にエレベエーター若しくは階段で荷上げなどを行いますが、その搬入経路の幅や高さ、奥行きなどを事前に確認して搬入できるサイズにしておく事は重要です。 また、地下階に置いては昨今の気象状況で大雨による地下階の浸水などの被害も深刻になってきておりますので、有事の際の時にどの様に対処するかも設計段階で設計士の方とよく検討されておいた方が宜しいかと思います。
ご参考になれば幸いです。 -
匿名さん 2020-12-14 09:51:44.0投稿
流儀
業種にもよりますが、消防法などの規制が高層階同様に厳しくなりますので、特に火を用いる飲食店舗等では電化厨房などの工夫が必要となります。
その他の店舗も含む一般的には外光が得れませんので、終日照明が必要となり、観葉植物などの持ちが悪い点が弱点であり、近隣店舗の匂いが店内にも入りやすい点が弱点でもあります。
然し、年間を通して外気温が変わらぬ為、エアコン等の光熱費が比較的一定である点はメリットでしょうか。
-
匿名さん 2020-11-16 09:42:26.0投稿
流儀
こんにちわ。 なんといっても水回りでしょうか。例えばトイレや洗面、手洗いなど排水をどうやって道路に埋まっている下水道管に接続するかがポイントになります。 その地下のテナント部分がもともと貸店舗として貸し出す予定で計画されているのであれば、そういった設備部分にも配慮されていると思いますが、そうでない場合は気を付けてください。
どうように、空調は換気のダクトがしっかりと外部に出ているか、もしくは出せるかを確認する必要があると思います。
ご参考になれば。
-
山上 浩明 2020-03-09 10:28:31.0投稿
流儀
機能的には、給排気です。給気と排気のバランスが悪くなりがちです。排気が強すぎるケースがよくあります。お店に入るとき、扉が重たくなって開けにくいということを経験したことはございませんか?(掃除機のイメージ)そういうお店にならないようにしないといけません。わかりやすい事例をご紹介いたしました。
-
流儀
B1Fなどの地階でテナントを検討する場合は、設備関連を特に留意いただきたいです。地下という性質上 増設などを簡易的に行える物件は少ないので入居を施主様が決める前に必ず条件の確認を行います。
合わせて店舗である場合動線的にも単独動線をもつ場合が多いため、サインやファサードの計画についてもイメージをしておくことが大事だと思います。 -
流儀
地下物件につき留意するポイント。
<ソフト面>
・必ず目的を持って来店が望める業態以外、誘導性のあるアプローチ及びサイン計画が出来る環境か否か。
・厨房器具等の大型機材の搬出入経路の確認。
<ハード面>
・インフラの確認。飲食関係の場合、特に一般給換気、厨房給排気のルート確保が(ダクトサイズ、数、出入口開口サイズ)重要。
<他>
・特に飲食及び風営法興行場法に関連する業態は消防法等の確認も重要。
・湿気及び地下特有の臭気の懸念が払拭できない事例も有り注意が必要。 -
流儀
地下テナントは、設備の増量工事が難しい場合も多いので、給排水・換気・空調・電気容量の確認が必須です。また、湿気も高いので仕上げ材NI調湿機能を持ったものを選ぶなど工夫が必要です。
-
匿名さん (デザイン・設計) 2017-11-24 09:55:28.0投稿
流儀
施工する上で注意するのは、やはりインフラの状況がどこまで整っているのかということです。
給排水設備状況、空調設備など新たにダクトなどが新設できないケースがありますのでその辺の注意はテナントを借りられる時に入念に確認をされていた方がいいと思います。建材の搬入搬出も困難であるほど、建築費がかさみますので、予め考慮頂く必要性もあります。
ただ空間つくりとしては、地下も地上も同じようなデザイン性で造れますのでその辺は安心されて大丈夫かと思います。
-
匿名さん 2017-11-21 11:26:54.0投稿
流儀
地下である事がメリットとなる店舗は、熱心なファンがわざわざ来てくれる強い個性を持つお店だと思います。その場合には特別な苦労はないでしょう。しかし一般的な業態で地下に出店せざるを得ない場合には、お客に「地下ならでは」と思わせる個性的な提案が必要でしょう。
1、目立つサイン
2、距離を感じさせない工夫
3、期待感の演出
など共用部分で個性を主張する全ての造作にはビル側の同意が必要です。ビル側との交渉力。そしてディメリットをメリットに変えられる想像力。この2点が不可欠です。
-
流儀
B1階での飲食店設計では、吸排気設計の確認が重要です。
すでにあるダクトを利用することが多いため、設置できるガス設備が限られたりします。
また、ビル全体の排水や受水槽などがB1フロア内部からの点検が必要の場合が多いので、
年に1~2回ビル設備管理業者の出入りが発生したりします。
その場合、レイアウトもビル側メンテナンスができるように設計する必要があります。
その他には、既存壁。または天井面に漏水の跡があるかをチェックしたほうが良いですね。
老朽化に伴い、すでに漏水している場合、内装工事でいくら気を付けても建物が漏水していてはカビが発生してしまいます。
デメリットにも感じますが、家賃などが安いことも多いため、何かが起きる前にたくさんの確認をしたうえでのお店作りをオススメします◎
-
匿名さん 2017-11-13 11:05:00.0投稿
流儀
大きく分けるとポイントは、①インフラ、②誘導(サイン)、③仕上げ の3つになります。
①インフラ
地下の場合、給気や換気などの配管ルートや開口(出し口)が限られてしまうため、インフラを考慮した計画を考えなければなりません。
②誘導(サイン)
地下へ誘導する為のサイン計画も必要です。事前に地上でサインが出せる位置を確認する事をおすすめします。
③仕上げ
地下は湿気がたまりやすいため、仕上も注意が必要です。
-
匿名さん 2017-11-13 08:59:16.0投稿
流儀
地下階は賃料が割安になるので魅力的ですよね。ただ、やはり地上階と違ったデメリットも出てきます。
設計としては、まず地下である制約です。日照がない場合は日中の照明計画もしっかり練らないといけませんし、地下であるぶん店舗のアピールの仕方も地上階より綿密に練る必要があります。
また、費用面では設備類がどのようなルートでおさまっていくのかでもだいぶ変わります。空調なら室外機置場の問題、排気ダクトのルート、給排水やガスの引込み距離など。割安な賃料にひかれて出店してみたら、設備系で初期投資がかさむ・・・なんてことも。
施工面では地下ゆえに搬入搬出の問題。設備系の引込みルートなどの設計と同じ悩みもありますね。
いずれにせよ、なぜ地下階を出店候補に選ぶのかを明確にしておく必要があります。地下階でも繁盛して地上まで行列をつくっている店舗は見かけます。賃料を抑えてこだわっている食材費に回したい、隠れ家的な使い方なので地下の方が向いている、音の問題などで地下だからこそ出店したいetc…
デメリットの把握も大事ですが、それら全てをふっとばすようなメリットやこだわりがあれば、地下でおもしろい事を計画するのはアリだと思います。
-
匿名さん 2017-11-10 11:48:06.0投稿
流儀
アプローチが2つ以上あれば、搬出入経路と客の動線、2方向避難等が簡単なので自由に考えられますが、そうではない場合は、それに適したレイアウトや設備、ストックヤード等を最初に考えてからデザインに入ります。
施工も搬出入経路が限られるので、資材置場やスケジュールを綿密にチェックします。
自分に合ったデザイン会社が見つかる!
お店のイメージを登録するだけで、平均7社から提案が受けられます。